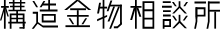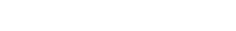近年、業務改善や建物の維持管理の観点から、建築・建設業界ではBIM活用が促進されており、「BIM」という言葉を聞くことが増えていると思います。木造でもBIMが整備されつつあり、BIMの取り組みを始めたプレカット会社も少しずつ増えてきています。
接合金物においても、BXカネシンからBIM用のデータが一般公開されましたが、接合金物のBIMと聞いても活用方法が分からないという方も多いと思います。そこで今回は、接合金物をBIMでモデル化したときの活用例とそのためのデータの作り方をご紹介いたします。なお、本コラムでは、BIMソフト「Revit 2021(Autodesk, inc.)」を用いております。
❶はじめに
BIM(Building Information Modeling)は、建物の3次元的な形状だけでなく、建築物としての情報やパーツの情報などを含んだデータです。そのため、設計・積算・施工・履歴管理など様々な目的で活用することが期待されています。
情報を多く含むことで使える用途は多くなる一方で、データとしては大きくなり作業性が悪くなるため、目的に応じてどこまでの情報量を入力するか(LoD)をあらかじめ整理しておくと効率的です。
❷ファミリの組み合わせ
Revitでは、建物を含む全体のデータ(=BIM)を「プロジェクト」、プロジェクトを構成するパーツを「ファミリ」と呼称し、ファミリを組み合わせてBIMデータを作成します。もう少し具体的に説明すると、柱は柱ファミリ、梁は梁ファミリ、接合部は接合部ファミリとしてプロジェクトに配置し、一つの建物データを作成します。

現在、BXカネシンのユーザー専用ページからダウンロードできる接合部のファミリデータは、商品コードと紐づいて作成されているため、製品によっては、金物と一緒に使われる付属品がセットになっていません。例えば、プレセッターSUでは取り付ける部材の幅に応じてドリフトピンやボルトの長さが変わるため、プレセッターSU単体・ドリフトピン・ボルトでそれぞれ別の商品コードとなっており、プレセッターSUの公開されているデータは下の画像のように梁受け部分のみの金物データとなっております。(製品に付属品がついているかどうかは、カタログに記載されておりますのでご確認ください。)

プレセッターSU・ドリフトピン・ボルトをそれぞれ別々にプロジェクトに配置していくこともできるのですが、全ての箇所に手で配置していく必要があるので、手間や時間がかかります。
そのような手間を省くために、まずは、プレセッターSU・ドリフトピン・ボルトをセットにしたファミリの作成方法を紹介します。(Revitでは、今回のように、ファミリを組み合わせて新たなファミリとすることができます。)
Revitの機能として寸法などを変数(パラメータ)として入力でき、その数値を組み合わせごとに「タイプ」としてファミリ内に設定することができます。
例えば、タイプAではドリフトピン長さ103mm・ボルト長さ130mm、タイプBではドリフトピン長さ103mm・ボルト長さ145mmとして、ファミリ内に保存することができます。
この機能を利用して、梁組や材幅、座彫りの有無などの組み合わせによって、自動的に長さが変わるような、プレセッターSU・ドリフトピン・ボルトがセットになったファミリを作成します。PS-39SUとPS-24SUが組み合わさるファミリの作成例を下に示します。

他の組み合わせについても同様に作成します。
❸使用例
❸-1 積算
❷のRevitイメージ図に記載したBIM(プロジェクト)を例に、金物の個数を積算します。
まずは、建築の柱・梁をモデル化し、接合金物が必要な個所に作成した接合部ファミリを部材断面に応じて配置します。
構造接合の集計表を開きます。Revitでは配置した金物の個数をタイプごとに集計することができます。

❷で部材の幅ごとにタイプを作成したため、一つのタイプに対して使用するボルト長さ・ドリフトピン長さが確定します。そのため、タイプと個数で集計表を作成しエクセル等に出力することで金物の個数を積算することができます。

❸-2 納まり確認
❷で作成したデータは積算はできますが、そのままでは納まりを確認することができないため、使用するボルト孔の選択や木の加工を追加で入力する必要があります。
入力方法の例を下に示します。なお、加工寸法については使用する製品のマニュアルをご確認ください。(今回は、プレセッターSUマニュアルに準じてデータを作成しております。)

上記の設定を入力すると実際と同じような納まりでBIMを作成することができ、干渉等を確認することができます。

上記で紹介した情報以外にも一つの接合部ファミリに様々な情報を含ませることができますので、目的に応じて自由に作成してみてください。
ただし、❶でも軽く記載しましたが、1つの建物に使われる接合部はかなりの数になると思いますので、接合部ファミリに情報を詰め込みすぎる(LoDを高くしすぎる)と、建物全体のデータ量が大きくなるためご注意ください。
❹おわりに
今回は接合部のBIMの活用例についてご紹介しましたが、そもそもBIMソフトを持っていない方もいると思います。ユーザー専用ページからダウンロードできるBIMのzipデータの中には、3次元形状を確認できるPDFデータも含まれておりますので、興味のある方はダウンロードしてみてください。
また、今後ご要望があれば組み合わせたファミリデータや便利ツールの作成も検討しますので、ご気軽にご相談ください。
今回のコラムはいつもと毛色が違う内容でしたが、参考になった方はぜひ「いいね」をお願いします。
今回は接合部がメインのため、BIMについて軽い説明しかしておりませんが、そもそもBIMとは何かを詳しく説明するコンテンツも今後公開する予定ですので、お楽しみに!
今回のコラムはいつもと毛色が違う内容でしたが、参考になった方はぜひ「いいね」をお願いします。