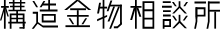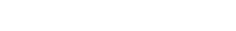木造で跳ね出しなどをする場合の手法の一つとして枕梁があります。
特に以下のような場合、枕梁がよく用いられると思います。
- 2方向跳ね出しとしたい場合(1方向は通常の跳ね出し、もう1方向は枕梁)
- 跳ね出し梁としたいが直下に柱がない場合
- 製材や既存梁の梁補強したい場合

原則、枕梁下に耐力壁は設けないことが一般的かと思いますが、耐力壁を併用した場合の接合部の考え方に関して紹介します。

❶梁と枕梁間のせん断力
地震時に「床合板→梁→枕梁→耐力壁」まで応力伝達させるため、
梁と枕梁間のせん断力の伝達を考える必要があります。
ロールパイプ10を用いると、梁のせん断力の処理がしやすいかと思います。
ちなみに、ロールパイプ10ではなく、面材壁でせん断力を処理する場合、
面材を継ぐ分、せん断剛性は多少落ちていると思われますので、両面張りとする、釘打ちを増す等、適切な判断が必要です。
❷柱頭の逆せん断耐力・引張力
金物工法としておけば、柱頭の逆せん断力は比較的処理しやすいように思えますが、
プレセッターSU梁受金物では、ノーマル孔からダウン孔に変更しても、柱側ボルトの端距離7d(=φ12×7=84)が確保できません。
端距離75mmのため、終局時に脆性破壊する恐れがあります。
そのため、筋かい系耐力壁や真壁耐力壁で柱頭に逆せん断力が入る場合は、避けることが望ましいです。
致し方ない場合、柱の割裂補強としてボルト接合での補強を推奨します。
また、ホールダウン金物を併用しないと引張力の処理が厳しいかと思います。
プレセッターSU梁受け金物のボルトと干渉しないように注意が必要です。
❸おわりに
枕梁に耐力壁を設ける場合について紹介しました。
「この場合の接合部について提案してほしい」等、実物件でお悩みがありましたら、構造金物相談所までご相談ください。
枕梁の使い方として、コラムが参考になりましたら、↓のボタンをクリックをお願いします。