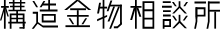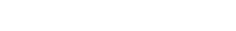壁倍率7倍を超える耐力壁を使用するとき、許容耐力は満足しても、変形がNGになることはありませんか。そんな時、フレーム解析で解決するかもしれません。今回は、柱頭柱脚にバネを入力したフレーム解析についてお伝えします。
❶はじめに
中大規模グレー本では7倍超の高耐力壁において、耐力壁のロッキングの影響があるために、柱脚金物の引張・圧縮剛性を考慮する方法が明示されています。
変形の増大が厳しいため、フレーム解析で多少なりとも緩和したい所かと思います。 フレーム解析のモデル化方法含め、どの程度変わるのかを比較してみたいと思います。
❷解析モデルの諸元
比較するモデルは以下の通りです。1フレームで2階建てを想定して比較します。 フレーム解析モデルは2パターンで検証してみます。
①N値計算ベース(階高は実際に合わせる)
②併用バネモデル(圧縮・引張ばねを簡易化したモデル)
③実状バネモデル(実際の納まりに近いモデル)
解析モデルの諸元としては、
- 柱梁は、構造用集成材E105程度(E=10,500N/mm2)とします。
- 部材断面は、柱105角、梁105×300、土台105角とします。
- 壁倍率10倍相当でブレース置換します。
- 柱頭柱脚バネは一律、高耐力フレックスホールダウン60を想定します。
(ここでは座金の剛性は考慮しません。また試験時3mm時耐力でバネを設定します。) - 1階柱脚部の支持条件はピン接合とします。
- 地震力は総2階を想定してAi分布が1.2程度のままに、1階耐力壁の許容せん断耐力と反力の合計が釣り合うように地震力を設定します。


❸水平変位の比較
2階床レベルの水平変位を比較すると、1/120rad時の変位は3000/120=25mmに対して、フレーム解析では30mm程度と2割増の変形増大となります。
対して、中大規模グレー本の計算式では安全側に梁の曲げ戻し効果をみないため5割程度の変形増大がかかり、厳しい結果です。 フレーム解析が有利な印象です。
❹ 応力の比較
1階柱脚接合部に生じる引張力比較、フレーム解析モデルの応力比較を示します。
フレーム解析モデルでは、N値計算に比べて中柱脚部に効果はないですが、隅柱の引張力低減が確認できます。
また『③実状バネモデル』では、梁の曲げ戻し効果を適切に考慮でき、梁の曲げモーメント・せん断力が厳しい場合に活用できそうです。



❺おわりに
今回の『③実状バネモデル』をモデル化するには、フレーム解析ソフトではひと手間かかります。
できれば避けたいモデル化ですが、2025年2月に一貫構造計算ソフトウェアWOOD-ST(株式会社構造システム)がこのモデル化に対応したようです。是非ご活用ください。
また、今回は2階建てで検討しましたが、より階数の多い連層耐震壁等、梁の曲げ戻しの影響が大きい場合、より顕著に影響がでてくると思われます。
不明点があれば、構造金物相談所までご相談ください。
構造システム様とコラボ
2025年9月追記
「構造設計コラムvol.32 柱頭柱脚のモデル化について」の中で㈱構造システム様の「WOOD-ST」をご紹介したところ、コラボ企画として同社のnoteにて実作業時のモデル作成などを解説したトピックスを掲載頂きました。ソフトの画面を使って入力から結果の見方まで解説頂いています。是非ご参照ください。
note 構造システム・企画室から
【高耐力壁×ホールダウン金物】設計者の悩みに応える実状モデル
柱頭柱脚のモデル化の考え方として、コラムが参考になりましたら、↓のボタンをクリックをお願いします。