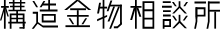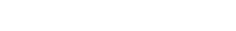構造設計コラムVol.20では梁を2丁合わせとして一体化させる際の注意点をご紹介しましたが、実際に2丁合わせ梁を使う場合、梁受け金物はどうすればよいかお困りではないでしょうか。
今回は、2丁合わせにした場合の梁端部の納まりについて、ご紹介いたします。
❶はじめに
一般的に2丁合わせ梁の納め方は下記の2種類が考えられます。
①2材の間に梁受金物をつける
②それぞれの梁に梁受金物をつける

TS金物のようなシングルスリット梁受けの場合、①②両方可能ですが、②だと適用条件が150幅以上のため、最低でも150幅を2丁合わせにする必要があり、木材の費用が高くなる可能性があります。
プレセッターSUのような既製品のダブルスリット梁受の場合、①は加工が難しいため、②になると思います。
❷2材の間に梁受金物をつける場合
TS金物を例として考えます。
梁受金物を中央に取り付ける場合、引張力が生じると、下の図のように端部が開く可能性があります。

そのため、端部をボルトなどで留めることが望ましいですが、既製品の金物は形状が決まっているため、開き止めのボルトなどを通す孔がありません。そこで、ドリフトピンをボルトに置き換え、開き止め兼曲げ降伏型接合具として使用します。

TS金物では、耐力を計算にて算出しており、木質構造設計規準・同解説やEYT式などの理論によると、ボルトを用いる場合とドリフトピンを用いる場合の耐力算定手法はほとんど変わりませんが、ボルトを用いるとロープ効果が生じるため、同じ支圧面積であればドリフトピン接合の耐力以上となります。
上記の理由で、ドリフトピンをボルトに置き換えても問題ないと考えられますが、検証のため社内試験で耐力が問題ないことを確認しております。詳細については、TS金物 掛け梁2丁合わせ説明資料をご確認ください。
(「TS金物 掛け梁2丁合わせ説明資料」は、BXカネシンのホームページのユーザー専用ページ(データダウンロード>マニュアル・設計ツール)よりダウンロードできます。
ダウンロードするには初回のみユーザー登録が必要です。)
❸それぞれの梁に梁受金物をつける
1か所の梁端部に対して1つの梁受金物がついているため、2丁合わせの掛け梁側の耐力は梁受金物2個分の耐力となると考えられます。

また、受け材側(ボルト側)については、ボルトの間隔が掛け梁1本分の幅となるので、最低でも105mmとなります。『木質構造設計規準・同解説』に繊維直角方向の力を受けるボルト間隔は5d(d:ボルト径=12mm)以上との記載があり、105mm<5d(60mm)なので2丁合わせで使用することによる耐力低下は生じないと考えられます。
よって、受け材側の耐力も梁受金物2個分の耐力となると考えられます。
上記内容については、検証のため社内試験で耐力が問題ないことを確認しております。詳細は、プレセッターSU2丁合わせ説明資料をご確認ください。
❹ おわりに
荷重条件が厳しい場合や燃えしろ設計をする場合、部材を検討すると断面が大きくなり特注部材になってしまうこともあると思います。そのようなときに、一般流通材を組み合わせて2丁合わせ梁とすることで、コストを抑えることができるかもしれません。
今回のコラムや構造設計コラムVol.20などをもとに、2丁梁を検討してみてはいかがでしょうか。
不明点があれば、構造金物相談所までご相談ください。
2丁合わせ接合部の考え方として、コラムが参考になりましたら、↓のボタンをクリックをお願いします。