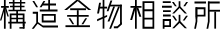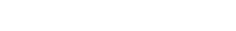構造設計コラムvol.20では2丁合わせ梁について、構造設計コラムvol.21では耐力壁の2重配置についてご紹介しました。このような場合に、柱も2丁合わせとすることが多いと思いますので、今回は2丁合わせ柱の設計例について紹介します。
目次
- はじめに
- 設計方針と計算結果
- 座屈耐力の比較
- おわりに
1. はじめに
105幅の梁を2丁合わせで使用する際、梁を受ける柱を210角とすると梁幅と柱幅が同じになるため、納まりが楽になります。柱を210角とする際の選択肢としては、
①105×210の柱を2本並べる
②105×210の柱をビスを使用して2丁合わせとする
③210角の1本材とする
が考えられます。
上記それぞれの場合について座屈耐力を算出し、比較してみます。
以下、②に関して設計例として既往の評価式を参照して座屈耐力を算出します。
2. 設計方針と計算結果
柱を2丁合わせとした上でビス止めする場合の設計方針は以下の通りです。
- 柱相互のヤング係数の差異が座屈耐力に影響しにくいように、製材ではなく、オウシュウアカマツ対称異等級構成構造用集成材E105-F300を採用します。
- 柱どうしの接合はMPオールスクリューを使用し、斜め45°打ち@300mmで接合した場合(BXカネシンの社内試験データを参照)と、垂直打ち@200mmで接合した場合(第三者機関で取得した評価書のデータを参照)について検討します。
(MPオールスクリューを集成材に打ち込む方向は、評価時では強軸方向に打ち込んでいるため、実際にはラミナ強度やビスを打つ方向に応じてビスのせん断剛性を低減するか、打ち込み位置に注意する必要があると思われます。また、評価外の使い方のため適用の可否は設計者判断となります。) - MPオールスクリューの剛性は、斜め打ちは初期剛性の平均値、垂直打ちは評価値を適用します。
- 計算方法は以下の参考文献を参照します(B.の理論を元にしたA.の式にて計算)
参考文献
- 足立亘他,スギ製材を用いた長ビス組立柱の座屈性能,日本建築学会学術講演梗概集(北陸),2019.9
- 沢田稔,釘着重ね柱の座屈長さ,北海道大学農学部 演習林研究報告37(3),pp.747-758,1980

計算結果は以下の通りです。

3. 座屈耐力の比較
座屈耐力を比較すると以下のようになります。
柱相互を斜めビス止めすることで、
②2丁合わせの柱をビス止めした場合/①柱を並べたのみの場合 ≒ 2.1倍
②2丁合わせの柱をビス止めした場合/③柱を1本材にした場合 ≒ 0.8倍
となっており、①柱を並べたのみの場合に比べると座屈耐力が大きく改善することが確認できます。
3、4階建て等、座屈耐力が厳しい時には検討を推奨します。 ただ、施工手間を考えると、ビスの垂直打ち接合ですませたいところです。
4. おわりに
今回は柱軸力が理想的に生じる場合を想定して検討しましたが、
実際の建物では以下のような課題が想定されます。
- 耐力壁の付帯柱などでは、片側の柱に軸力が偏在しうる。
- 通し柱では柱に曲げモーメントが生じうる。
そのため、例えば、
- 短期荷重分は柱1本の耐力で問題ない程度に設計する。
あるいは、柱脚金物も考えると、別途柱を添えて、その柱で短期荷重を処理する。 - 詳細計算法の耐力壁であれば、釘打ちをそれぞれの柱に設けて軸力を均等に作用させる。
- 長期荷重時の軸力が厳しい場合のみの適用とする。
- 曲げが生じる場合を想定して、上記座屈式のCkではなく、
木質構造接合部設計マニュアルの組立梁のCulを適用する。 - 安全を見て2丁合わせ柱に接着剤(パネルボンドKU等)も併用する。
等、適切な設計者判断が求められます。
また、柱を1本材にした場合と比較して、ビス止めによる2丁合わせ梁のコストメリットは確認が必要ですが、手加工になりがちな斜めビス打ち用の先穴なしで、垂直打ちにより施工できれば、十分にメリットがあると想定されます。
今回の設計例では、計算式に日本建築学会学術講演梗概集から引用している部分もあり、
実務レベルでの運用は審査機関等に事前に相談したほうが無難でしょう。
関連するコラム:vol.21 耐力壁2重配置の注意点 vol.20 2丁合わせ梁の接合部の注意点
Keyphrase : #合わせ柱 #複合部材 #構造用ビス #座屈
コラムで使用した製品:MPオールスクリュー