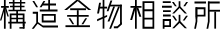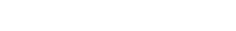ドリフトピン接合はラグスクリューボルト接合やGIR接合に次いで耐力が高いですが、vol.25で紹介したボルト接合などに比べ、接合金物分コストと手間がかかります。
例えばトラス構造の場合、まずはウッドタッチや引きボルトによるJISトラス、あるいは、既製品としてMPネジ接合システム等で検討し、どうしても厳しければ、または意匠的に要望があれば、ドリフトピン接合等を使うことになるかと思われます。

今回はドリフトピン接合で配慮したいことに関して紹介したいと思います。
❶ドリフトピンの打ち込み本数と径をどの程度にするか
ドリフトピンは多すぎると納まりません。多少の施工誤差が蓄積されるためです。Φ12なら数が多くても無理やり打ちようがあります。
Φ16が理想ではありますが、Φ20くらいまでなら割と打ちやすいです。それ以上になるとかなり打ちにくくなってきます。最大でもΦ24くらいまでには抑えたいところです。
あまりにも高耐力が必要であれば、柱脚金物では通し柱、梁受け金物では二丁合わせ梁やプレートやLアングルなどによる顎や添え柱で梁を受けることを推奨します。
❷先端のテーパー長さをいくつにするか

構造設計では支圧耐力を確保したいために、テーパー長さはできるだけ短くしたいですが、テーパー長さが3mm程度では、施工しにくさがあります。
住宅用金物のように10mmが理想、最低でも5mmは設けたいところです。
ただ、テーパー部が長かったり片側だけであったりすると、特に径が太い場合には終局時にバランスよく荷重負担しにくくなりがちです。
ただ、計算による場合であれば、十分余力があるので片側テーパーでも問題無さそうではあります。
❸SS400のドリフトピンと住宅用ドリフトピンは同じ性能なのか
構造設計の場合、計算の都合からドリフトピンはSS400にしたいところだと思われますが、適宜製作が必要です。
住宅用金物で使われるドリフトピンはSS400ではないですが、六角ボルトの線材ベースなので強度区分4.6、4.8相当であり、設計者判断で使用できる可能性があります。
高耐力柱脚45の短期基準引張耐力について、実験耐力と計算耐力を比較してみます。
実験耐力(試験成績書):45kN
計 算 耐 力 ( E Y T ) :7.5kN/本×4本=30kN
上記の計算であっても、十分余力はあることが確認できます。
実験結果を参照すれば、設計時の根拠になりうるかと思われます。
❹最後に
設計時には上記以外にも配慮すべきポイントが多くありますので、設計時に各種文献を十分確認の上、適切に設計してください。
2丁合わせ梁など梁幅が大きい場合には、ボルトと同様に、強度区分10.9ドリフトピン(高強度ボルトの線材使用)を用いるとΦ12等、径が小さいままに高耐力を確保できます。径が小さいので、施工上も有効です。
受注生産(1000本程度~)となるため、比較的大規模物件に限りますが、強度区分10.9での社内試験結果は提供可能です。 使用したい場合には構造金物相談所までご相談ください。